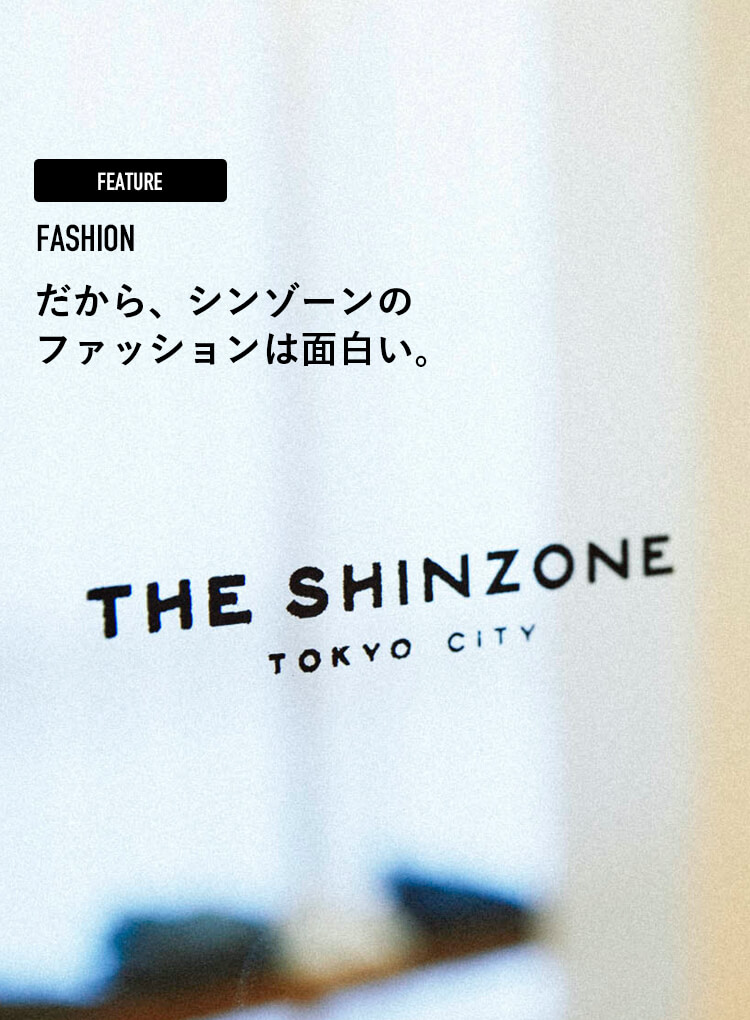この春からFigure Onlineでの展開がスタートしたシンゾーン。すでに高い人気を集めるブランドですが、
その魅力はどこにあるのか? ファッションとの向き合い方、コンセプトメイキング、クオリティの追求。
クリエイティブディレクターの染谷さんにお話を伺いました。
その魅力はどこにあるのか? ファッションとの向き合い方、コンセプトメイキング、クオリティの追求。
クリエイティブディレクターの染谷さんにお話を伺いました。
この春からFigure Onlineでの展開が
スタートしたシンゾーン。
すでに高い人気を集めるブランドですが、
その魅力はどこにあるのか?
ファッションとの向き合い方、
コンセプトメイキング、クオリティの追求。
クリエイティブディレクターの
染谷さんにお話を伺いました。
スタートしたシンゾーン。
すでに高い人気を集めるブランドですが、
その魅力はどこにあるのか?
ファッションとの向き合い方、
コンセプトメイキング、クオリティの追求。
クリエイティブディレクターの
染谷さんにお話を伺いました。
世界中のファッションストアがひしめく表参道。メインストリートからほんの少しだけ路地に入ったところにあるビルの3階にシンゾーンのフラッグシップストアはあります。以前あった場所から移転してオープンしたのが、2019年11月のこと。取材当日は1月の半ば。まだまだ新しさが香るお店でした。
『ようこそいらっしゃいました』。気さくな笑顔で迎えてくれたのは、シンゾーンのファウンダーでありクリエイティブディレクターの染谷真太郎さん。『今日はお店が休みなので、ゆっくり見て行ってください』。そう言って温かいコーヒーを差し出してくれました。

染谷さんにお会いして、まず聞いてみたいと思ったこと。それは『その飽くなき洋服への愛情はどこからくるんですか?』ということ。これまでも様々な媒体で染谷さんの取材記事を見てきたし、公式のHPのDIRECTOR’S BLOGでも近況を見てきたけれど、服作り、バイイング、お店作りとどれに対しても向き合い方が真摯。ファンでいてくれるお客様のために旗艦店ではセールをしない決断をしたりと、本当に服に対する姿勢には感心させられます。
「セレクトショップとしてシンゾーンをオープンさせてから20年。初めはわからない事だらけで、至らぬことばかり。ただ格好いいものを仕入れて、それを買ってもらうだけ。そんな風にしか20代の頃は考えられませんでした。でもショップがちょっとずつ増えていくにつれ関わる仲間も増えてきて、自己満足だけでは済まされないようになってきた。バイイングの仕方も、作り方も、売り方も、全てにおいて喜んでもらわなければいけない。そう思えるようになったのは、ここ5、6年です」。
お客様だけでなく、関わる人みんなが満足でいられるように。『本当、単純な話なんです』と染谷さんは教えてくれました。

デザインで人を驚かせたい。昨日まで世の中になったものを創り出したい。そういう風に思うファッションディレクターも多いが、染谷さんはちょっと違う。大前提は人を幸せな気分にすること。
「なので、“売れるから”とか“トレンドだから”という観点で服を作ったりバイイングすることは、僕はほとんどない。ワードローブにこんな服が加わったらアガるだろうなー、っていう感覚で取り組んでいます」。
それは理想だけど、結果が伴わないと継続ができない。その辺のジレンマは感じない?

「もちろん。最初の3年くらいは売れなくて本当に大変でした(笑)。その時はもちろんお金で苦労したけれど、それはまあなんとか稼げばいい。それよりももっと、失ってしまうと取り返しのつかないものってあるじゃないですか。僕にとってはそっちの方がプライオリティは高い」。
もちろんその思いは、ものづくりにおいても同じです。
「ものを作るときはしっかり時間をかけて作りたい。そしてそれは長く愛されるものであって欲しい。そのためにはいろんな要素を兼ね備えておかなければいけないんです。売れそうないい感じのものを5つ作るんだったら、自分が心から納得するいいものを1つ作りたい。それを2年、3年、5年と長く作り続けたいというのが根本にあります」。
そしてそれを続けていくことでクオリティも上がってくると染谷さんは言います。
「繰り返し作るから、それを作る職人さんの腕も上がるんです。そうするとお客様も喜ぶし、職人さんにとってもいい。だから僕はそんなに、次から口に新しいものを作ることが大事だとは思っていない。核となるアイテムがあって、その上に積み重なるものがある。それが理想的なバランスだと思っています」。
シンゾーンが作る服のほとんどは日本製。
長く支持されるアイテムを多く生み出すことで、職人の技術の向上にも貢献できる。
長く支持されるアイテムを多く生み出すことで、職人の技術の向上にも貢献できる。


さて、そんなシンゾーンの根幹にあるアイテムといえば、ジーンズ。
ブランドコンセプトにも“デニムに合う上品なカジュアル”とあります。
そもそもそのデニム愛はどこから?
ブランドコンセプトにも“デニムに合う上品なカジュアル”とあります。
そもそもそのデニム愛はどこから?
「お店を始めるときにいつか必ず取り扱いたいと思っていたブランドが、メゾン・マルジェラとバレンシアガとマノロ・ブラニクだったのですが、当時のバレンシアガのディレクターを務めていたニコラ・ジェスキエールという人が(今はルイ・ヴィトンのレディースのアーティスティック ディレクター)、いつも素敵なデニムスタイルだったんです。それでデニムっていいなってずっと思っていたのが原点かなあ。『あんな天才もやっぱりリーバイスを穿くんだな』とか思ってました。それにマルジェラも古いデニムをリメイクしたプロダクトをリリースしていたり。とにかくそういうのが好きだった。それが自分のデニムに対する憧れの原点かな」。
さて、そんなシンゾーンの根幹にあるアイテムといえば、ジーンズ。ブランドコンセプトにも“デニムに合う上品なカジュアル”とあります。
そもそもそのデニム愛はどこから?
そもそもそのデニム愛はどこから?
「お店を始めるときにいつか必ず取り扱いたいと思っていたブランドが、メゾン・マルジェラとバレンシアガとマノロ・ブラニクだったのですが、当時のバレンシアガのディレクターを務めていたニコラ・ジェスキエールという人が(今はルイ・ヴィトンのレディースのアーティスティック ディレクター)、いつも素敵なデニムスタイルだったんです。それでデニムっていいなってずっと思っていたのが原点かなあ。『あんな天才もやっぱりリーバイスを穿くんだな』とか思ってました。それにマルジェラも古いデニムをリメイクしたプロダクトをリリースしていたり。とにかくそういうのが好きだった。それが自分のデニムに対する憧れの原点かな」。

シンゾーンのデニムは単純じゃない。ディテールにこだわるがゆえに作業効率は非常に低い。難しい縫製の仕方を取り入れ、細部に妥協しない。一見同じように見えるデニムでも、シンゾーンのそれが支持されるのは、そんな裏付けがあってこそ。
「シーズンによって股上の深さ浅さを調整したり、あとはどんな靴を合わせたいかを考えて裾幅やシルエットを変えたり。シンプルですがすごく奥の深いアイテムですね、デニムは」。
そんなふうに生み出されたデニムを軸に毎シーズンコレクションが展開されていく。その全体のインスピレーションはどこから得ているのか聞いてみました。
「根本にあるのはアイビーです。アイビールックを身にまとったハリウッドスターの写真集を持っているのですが、そこからインスピレーションを得ることが多いです。プラス、1960〜70年代くらいの映画。あともちろんパリやミラノのコレクションもチェックします。それらを一旦自分たちの中で消化した上で、『次はこれが着たいよね』っていうものを導き出す。シンゾーンのお客様のワードローブを想像した時に『こういうパンツはきっと持っているだろうから、次はこういう方が可愛いよね』とか。そうやってだんだん具現化していきます」。

単純なトレンドに対する回答じゃなく、ビジネス的な正解でもなく、“シンゾーン”というひとつのストーリーを創り出す。染谷さんがしている作業はそういうことだし、そこに多くのファンが共感しているのかもしれません。
「ファッションが大好きですからもちろんトレンドは気にします。でもそれよりももっと大事なものがある。耐久性とか普遍性とか。やっぱり長く着て欲しいと思って作っているので」。

「今季のテーマは『クラシックスポーツ』。ジョン・F・ケネディをアイコンにしていて、それにまつわる様々なものからインスピレーションを得ています。妻のジャクリーン、別荘があったところの名前、所有していた船の名前などですね。それにジョン・F・ケネディはスポーツマンだったので、コレクションもその要素が強め。今季はスポーティなアイテムが多いです」。
どこか既視感があるけれど新鮮。新しいけれど安心感がある。アイテムひとつひとつも素晴らしいけれど、どうせならルックごと取り入れてしまいたい。そんな風に思えるコレクションです。
DAMMY2019sscollection
「実は“既視感”っていうのはすごく大事にしているんです。ただ新しいだけのものは、僕は好きじゃない。発見と安心感が両方備わっている服が理想です」。
ブランドは今年で20周年。節目の年ですが、何か展望は?
「セレクトショップとして始まったシンゾーンですが、ゆくゆくはデニムブランドとして広く世界にも認知されたい。そのためにできることを模索していきたいです、それと、いつかメンズもできたらいいですね」。


オリジナルとセレクトが半々。フィッティングも広めに作り、のんびりとくつろぎながらショッピングが楽しめるよう工夫されている。「シンゾーンのホスピタリティを体感してもらうための空間です」(染谷)。
Photo_Kanta Matsubayashi Interview & Text_Juno Namekata
Photo_Kanta Matsubayashi
Interview & Text_Juno Namekata